特別講演
「消えるロボットを目指して40年 ― 生物型ロボットから宇宙ロボット・レスキューロボットまで ー」
日時
3月4日(火)16:00〜16:50
場所
常翔ホール
講師
松野 文俊(大阪工業大学工学部電子情報システム工学科 特任教授、京都大学名誉教授)
概要
消えるロボットとは何でしょう?講演の中でお話します。
地球上で生存している生物は、自然淘汰の末に生き残ってきたわけで、地球環境にうまく適応した証だと思われます。その意味でも、人工物を作るにあたって、生物の知を理解し、それを具現化することは重要なアプローチであると思います。生物から学び生物を超えるロボットを目指して、講演者がこれまでに創ってきたロボットや最近のプロジェクトの成果を紹介し、今後の方向性について議論できればと考えています。
講師略歴

松野 文俊(まつの ふみとし)君
1986年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。大阪大学、神戸大学、東京工業大学、電気通信大学を経て 2009年より京都大学大学院工学研究科(機械理工学専攻)教授となり、2023年4月より大阪工業大学(電子情報システム工学科)特任教授、現在に至る。京都大学名誉教授。福島国際研究教育機構ロボット分野副分野長、特定非営利活動法人国際レスキューシステム研究機構副会長を兼任。主に、ロボティクス・制御理論・レスキュー学に関する研究に従事。1989年度日本ロボット学会研究奨励賞、2018年度同学会論文賞、1993年度システム制御情報学会論文賞、2001、2006、2017年度計測自動制御学会論文賞、2001年度同学会武田賞、2017年度同友田賞、2009年度日本機械学会ロボメカ部門学術業績賞、2013年度情報処理学会論文賞などを受賞。専門は、制御工学、ロボティクス。特に、分布定数系・非線形系制御理論、群知能、超生物ロボティクス、過酷環境ロボティクス、ヒューマンインタフェースなどに興味をもつ。IEEE Robotics and Automation Society, Technical Committee on Safety, Security, and Rescue Robotics のCo-Chair、システム制御情報学会会長、日本ロボット学会副会長などを歴任。IEEE, システム制御情報学会(名誉会員)、日本機械学会(Fellow)、計測自動制御学会(Fellow)、日本ロボット学会(Fellow)、日本工学アカデミーなどの会員。
受賞記念講演
以下の受賞記念講演が開催されます.
パイオニア賞受賞記念講演
河野佑先生(広島大学)

[日時] 3月3日 9時30分~10時10分
[場所] 常翔ホール
[講演者] 河野佑先生(広島大学)
[題目] 単調性を基点としたネットワーク制御論
概要
IoT技術の発展に伴い,多数のサブシステムがネットワークを介して結合された系を制御対象とする機会が急速に拡大している.サブシステム数の変化に適応するためには,各サブシステムを自律分散的に設計し,ネットワーク全体として所望の特性を付与することが望ましい.そのための鍵として,講演者は「単調性」と呼ばれる性質に着目している.本講演では,単調性を基点にした解析・設計論の構築に関する講演者の取り組みについて,Contraction理論との関連を含めて紹介する.
略歴
2013年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了.京都大学特定研究員,フローニンゲン大学研究員を経て,2019年より広島大学大学院先進理工系科学研究科准教授となり現在に至る.博士(工学).2021年広島大学 Phoenix Outstanding Researcher Award(学長賞) を受賞.
パイオニア技術賞受賞記念講演
畑中健志先生(東京科学大学)

[日時] 3月5日 9時30分~10時10分
[場所] 常翔ホール
[講演者] 畑中健志先生(東京科学大学)
[題目] スマート農業とマルチロボットの協調 ~フィールド実験ができるまで~
概要
2010年代後半にドイツより提唱された Agriculture 4.0 は,環境保全のための農業ロボットの小型化・電動化とともに,小型ロボット群の協調による広域運用を謳った.一方,マルチロボットの協調制御理論は過去20年の研究によって高度に成熟し,社会実装のフェーズにある.本講演では,講演者の研究グループが経験した両者のはざまにおける奮闘と,理論構築からフィールド実験に至るまでの一連の成果を紹介する.最後に,Agriculture 5.0を見据えた,人とロボットの協調や植物工場における植物生育制御の可能性についても論じる.
略歴
2007年京都大学大学院博士後期課程修了.東京工業大学助教,准教授,大阪大学准教授を経て,2024年より東京科学大学教授となり現在に至る.Cyber-Physical-Human Systems の研究に従事.
著書:
- Passivity-Based Control and Estimation in Networked Robotics (Springer)
- マルチエージェントシステムの制御 (コロナ社)
- 機械学習のための関数解析入門(内田老鶴圃)
受賞歴:
- 2024年 SICE制御部門パイオニア技術賞
- 2017年 同木村賞
- 2014年 同パイオニア賞
- 2018年 同制御部門大会賞
- 2016年 SICE著述賞
- 2020年 同武田賞
- 2009, 2015, 2020, 2021, 2023年 同論文賞
- IFAC 2023 Application Paper Prize Finalist
- IFAC CPHS 2020 Best Research Paper Award など
博士(情報学).Annual Reviews in Control の副EiC, IEEE TCST のSE.SICE JCMSI など多数の学術雑誌AE,IEEE CSS CEB Member.第9回SICE MSCSプログラム委員長,第15回横幹連合コンファレンスプログラム委員長 などを歴任.IFAC CPHS 2026 Co-General Chair および DARS 2026 Program Chair.IEEE Senior Member.
特別セッション
第53回 制御理論シンポジウム 特別セッション
「JST ASPIRE-CPDS:国際頭脳循環と若手研究者国際交流の促進を目指して」
主催・企画
SICE 制御部門 制御理論部会
日時
3月3日(月)10:30~12:30
場所
常翔ホール
概要 (ASPIREより一部抜粋)
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の先端国際共同研究推進事業(ASPIRE:Adopting Sustainable Partnerships for Innovative Research Ecosystem)は,我が国の科学技術力の維持・向上を図るため,政策上重要な科学技術分野において,国際共同研究を通じて我が国と科学技術先進国・地域のトップ研究者同士を結び付け,我が国の研究コミュニティにおいて国際頭脳循環を加速することを目指すものである.すなわち
- 世界のトップ科学者層とのネットワーク構築
- 未来を決める国際的なトップ研究コミュニティへの参画
- 将来持続的に世界で活躍できる人材の育成
を支援する事業である.
2024年度のAI・情報分野における「TopのためのASPIRE」の公募に対して,制御を専門とする研究者による研究提案「サイバーフィジカルダイナミカルシステムの数理基盤創生:制御と予測・学習に関する学際的研究展開と人材育成」(略称:ASPIRE-CPDS)が採択され,2024年12月より活動を開始している.本特別企画では,ASPIRE-CPDSの概要説明,本プロジェクトに参加予定の若手研究者による推進中の研究内容,国際共同研究計画・研究展望などに関する発表を行うとともに,国際頭脳循環と若手研究者国際交流の促進のためにどのような取り組みが必要か,聴衆の方々とともに議論したい.
セッション構成
司会:永原正章(広島大学、SPIRE-CPDS 日本側副研究代表者)
- 「ASPIRE-CPDSで目指すもの」15分
九州大学 蛯原義雄 (ASPIRE-CPDS 日本側研究代表者) - 「ASPIRE-CPDSにおける国際頭脳循環・共同研究計画」15分
東京大学 石井秀明(ASPIRE-CPDS 日本側副研究代表者) - 若手研究者による研究発表
- 河野佑(広島大学)
- 鹿田佳那(九州工業大学)
- 岩田拓海(広島大学)
- Li Mengmou(広島大学)
- 田中大地(東京科学大学)
- 質疑・総合討論 15分
第11回 システム構築と制御技術シンポジウム 特別セッション
「制御技術から見た、産官学のトレンド(課題、ニーズ、例題等)は何か?」
主催・企画
SICE 制御部門 制御技術部会
日時
3月4日(火)10:40-12:40
場所
常翔ホール
講師(パネリスト)
小比賀理延氏 (ADAPTEX)
河合富貴子氏 (富士電機)
滑川徹氏(慶應義塾大学)
平田光男氏 (宇都宮大学)
堀川徳二郎氏 (TMEIC)
OS趣旨
制御理論の応用による制御技術の発展にフォーカスし、喫緊の技術的課題は何か?、あるいは、期待している(近未来の)技術は何か?、について話題提供とパネル討論によって深堀する。特に以下の点を念頭におく。
(1) 制御技術の現場での将来技術ニーズ、課題、注目される将来技術を紹介する
(2) 制御技術への関心のある理論研究者への情報提供を行う
(3)アカデミアからは、現在の研究トレンド、将来の期待テーマを紹介する
(4) 制御工学とその周辺に広がりが見える中、今後期待される工学テーマや重要技術は何かについて模索する
(5) 制御理論と応用の協調として、発展的に何ができるかを模索する
本セッションは、パネラーによる話題提供(12分間×5件)と パネル討論会(1時間)の構成で行われます。
招待講演
適応学習制御シンポジウム 招待講演
「陰的制御が持つ環境適応能力 ー事件は現場で起きているんだ!ー」
主催・企画
計測自動制御学会 制御部門 Society5.0に資する適応学習制御調査研究会
日時
3月5日(水)10:30-12:30
場所
Room 8 1105
講師
大須賀 公一
(大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻 教授)
概要
何事も無限定環境の中をうまく動かすには,身体と環境との相互作用を敵とはみなさずに味方とみなすことが肝要です.環境を敵とみなして戦いを挑むと作用反作用の法則からしっぺ返しをくらいます.私たちは相互作用が味方に見えるように工夫することができ,そのような状況になったとき,その相互作用を陰的制御と呼んでいます.実はこの陰的制御が環境の変化に対する適応機能を持っています.ここではそのような事例を紹介し,陰的制御が持つ環境適応能力について考察したいと思います.
講師略歴

大須賀 公一 (おおすか こういち) 君
1984年3月大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了.同年4月(株)東芝入社,総合研究所勤務.1986年10月大阪府立大学工学部機械工学科助手.その後,講師,助教授を経て,1998年5月京都大学大学院情報学研究科システム科学専攻助教授,2003年12月神戸大学工学部機械工学科教授,2009年4月大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻教授となり現在に至る.ロボティクス,制御工学,レスキュー工学などの研究に従事.工学博士.
誘導制御シンポジウム 招待講演
「小型月着陸実証機SLIMのピンポイント着陸達成と航法誘導制御技術の成果」
主催・企画
計測自動制御学会 制御部門 次世代航法誘導制御技術調査研究会
日時
3月3日(月)10:30-12:30
場所
Room 6 1007
講師
植田 聡史
(宇宙航空研究開発機構(JAXA) 研究開発部門 第一研究ユニット 研究領域主幹)
概要
SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) は宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(ISAS/JAXA)が開発した小型月着陸実証機である.SLIMは2023年9月7日にH-ⅡAロケット47号機で打ち上げられ,約4か月間の地球周回・深宇宙航行・月周回を経て,2024年1月20日に月面への軟着陸に成功した.その着陸精度が10m程度と評価されたことから,世界で初めてピンポイント月面着陸を達成したことが確認された.本講演では,SLIMミッションの全体像およびキー技術である航法誘導制御技術について概説し,ピンポイント月面着陸を達成するための研究成果,開発・運用における技術的挑戦について紹介する.
講師略歴

植田 聡史 (うえだ さとし) 君
2002年東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程修了.同年宇宙開発事業団入社.宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)の航法誘導制御系の開発,運用に従事.厳しい安全性が要求される宇宙ステーションへのランデブ飛行を航法誘導制御技術の面でリードし,連続成功に貢献した.欧州宇宙機関(ESA)訪問研究員を経て,現在,宇宙航空研究開発機構研究開発部門研究領域主幹.小型月着陸実証機(SLIM)の航法誘導制御系の研究開発および深宇宙探査ミッションのための航法誘導制御技術の研究に従事.SLIMプロジェクトでは大学研究者らとともに着陸降下のための誘導アルゴリズムを考案,世界初となるピンポイント月面着陸の成功に貢献した.
ワークショップ
ワークショップに参加される方は,参加申込時にチェックを入れてください.MSCS参加者は無料でご参加いただけます.また、会場の定員は100名となっております.
「超スマート社会の人流制御のためのモデル化」
日時
3月2日(日)午後13時~16時
場所
セミナー室201・202
概要
ウェルビーイングなスマート社会の実現では,人に着目したリソース制御が重要となっている.例えば,日本では,人材不足および労働時間規制による輸送力不足から,人の多い都市部の運輸・物流の停滞が発生し,輸送に関わる地域間のリソース調整が必要となっている.その一方で,IoT技術の発展から物理的な状態は時空間ともに高分解能で計測可能なことや,人工知能(AI)を介して人と機械を繋げるインタラクティブなサービスも展開され,人を中心とした計測制御のための技術が充足され始めている.本ワークショップでは,人や人流の制御に関わる周辺研究の有識者から,「人流制御ではどんなデータを扱うか,何がインプットとなるのか,何がアウトプットとなるか,何がゴールなのか」について講演頂き,聴講者の方々に当該分野におけるモデル化や制御の考えるきっかけを提供したいと考えている.
講師略歴
講演タイトル: 都市の人流データ計測と都市計画のためのモデル化について(都市工学視点)

長谷川 大輔 氏 東京大学 不動産イノベーション研究センター(CREI) 特任助教
略歴
2019年3月筑波大学システム情報工学研究科リスク工学専攻博士後期課程修了,博士(工学)2019年3月より(株)ディー・エヌ・エー,2020年7月より東京大学生産技術研究所を経て,2022年4月より東京大学不動産イノベーション研究センター特任助教に着任.都市計画,地域公共交通計画,空間情報科学に関する研究に従事
講演タイトル: 病院内の人の計測やソーシャルダイナミクスのモデル化について(ヒューマンコンピュータインタラクション視点)

山本 豪志朗 氏 京都大学 医学部附属病院 先制医療・生活習慣病研究センター 特定教授
略歴
2009年3月大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了.同年4月日本学術振興会特別研究員PD.同年7月岡山大学大学院自然科学研究科助教.2011年4月奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科助教,2016年4月京都大学医学部附属病院特定講師.2020年4月同特定准教授.2021年3月同准教授.2024年4月同特定教授,現在に至る.ヒューマンコンピュータインタラクション,拡張現実感,医療情報に関する研究に従事.情報処理学会,計測自動制御学会等会員.博士 (工学).
講演タイトル: 人間集団の行動変容への制御アプローチ(制御視点)
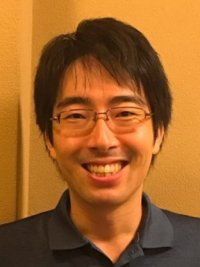
井上 正樹 氏 慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 准教授
略歴
2012年3月大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了,同年4月より科学技術振興機構 FIRST 合原最先端数理モデルプロジェクト研究員,東京工業大学大学院情報理工学研究科特別研究員,2014年4月より慶應義塾大学理工学部助教,2018年4月より同専任講師,2021年4月より同准教授となり現在に至る.2010年より2年間日本学術振興会特別研究員(DC2).博士(工学).Human-in-the-loopシステムに対する制御の理論と応用に関する研究に従事.計測自動制御学会論文賞(2013,2015,2018,2024年度),同論文賞武田賞(2018年度),同制御部門パイオニア賞(2019年度),システム制御情報学会論文賞(2014年度),電気学会産業応用部門論文賞(2017年度)などを受賞.IEEE CSS, SMCS, ITSS,計測自動制御学会,システム制御情報学会の会員.
コーディネーター役

澤田 賢治 電気通信大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター 准教授
略歴
2009年大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻博士後期課程修了.同年電気通信大学システム工学科助教,2015年同大学 i-パワードエネルギー・システム研究センター准教授となり現在に至る.博士(工学).2016年度計測自動制御学会制御部門大会技術賞,FA財団論文賞(2015年,2019年),2018年度日本機械学会賞(論文),2018年度油空圧機器技術振興財団論文賞,2018年度計測自動制御学会産業応用部門・技術賞,2019年計測自動制御学会制御部門パイオニア技術賞受賞.2016年より制御システムセキュリティセンター顧問.ハイブリッドシステムや制御系セキュリティに関する研究に従事.計測自動制御学会,システム制御情報学会,電子情報通信学会,電気学会,日本機械学会,IEEE会員.